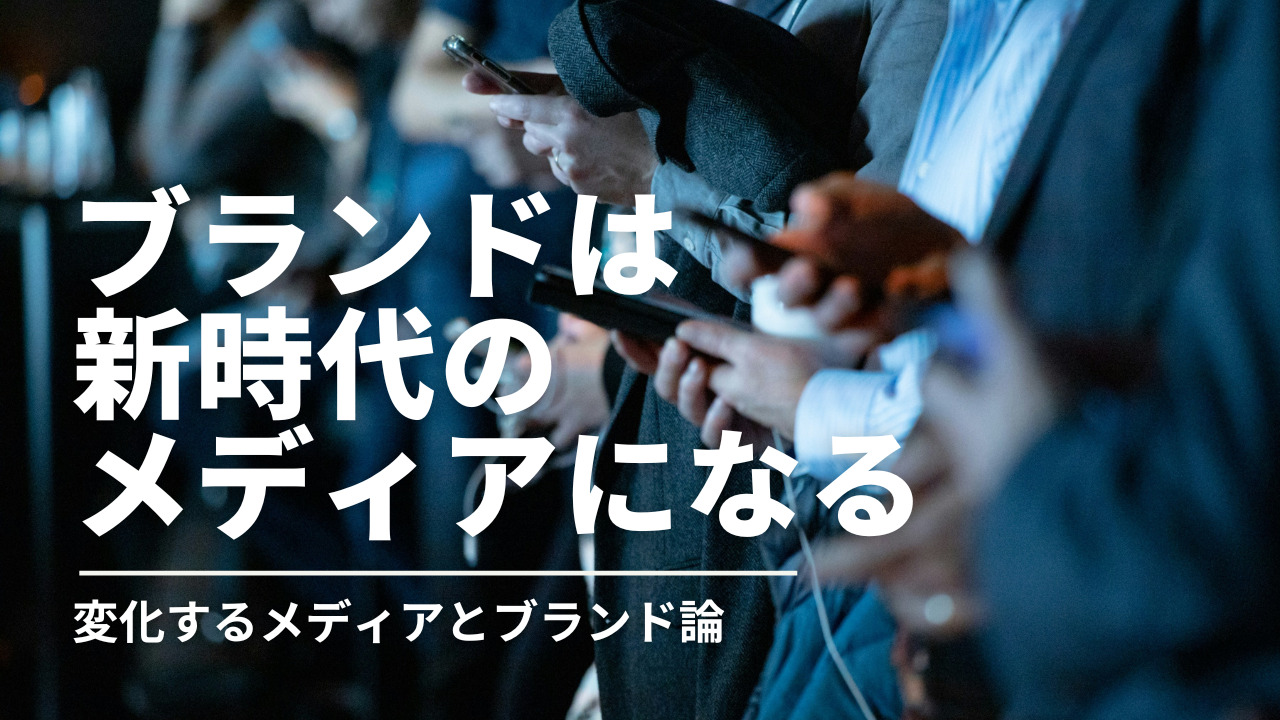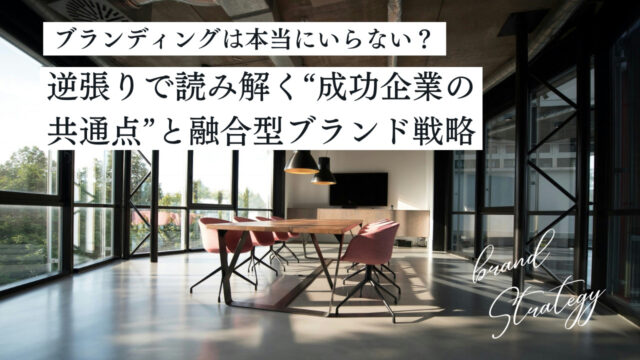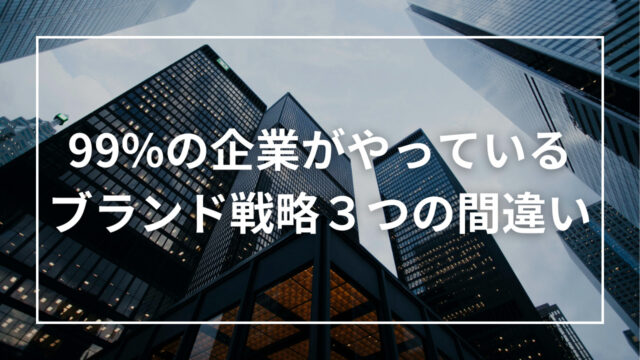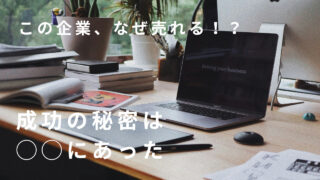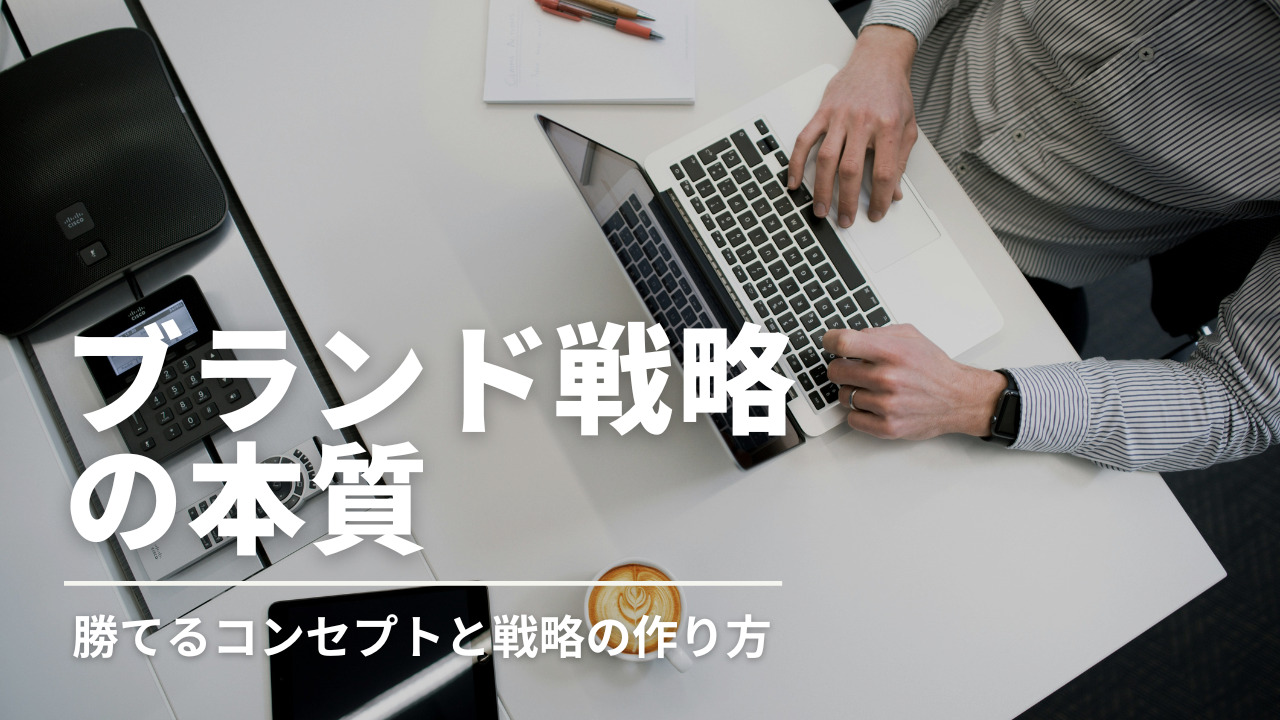
メディアの定義が変わる
従来のメディア定義は「情報を発信するための装置」だった。
新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、そしてウェブサイトまではあくまで情報は一方通行。
受け手は与えられた情報を咀嚼するか無視するか、選択肢は多くない。
でも、SNSの登場によってそれが大きく変化している。
現代では情報の双方向性だけでなく、第三者がコメントや引用することで多方向へと拡散していく。
それに伴って、メディアの概念が「共感を生むためのプラットフォーム」に変わりつつあるのだろう。
ここで言うブランドがメディア化するとは、単に情報を伝えるだけでなく、そのブランドを中心にコミュニティを形成し、価値観を共有する場を作るということを指す。
つまり、ブランドの役割がかつての商品やサービスの象徴から、情報発信や価値共有のプラットフォームへと変化していくのだ。
この事象をみると、かつては単に消費者の購買動機を刺激する存在だったブランドが、いまやメディアとしての役割を担い始めているように感じる。
企業の公式SNSがニュース媒体のように情報を届け、ブランドの姿勢や価値観を表現するわけだ。
ブランドの総合メディア化現象のようなものが広がりつつある。
なぜブランドがメディア化するのか
ブランドがメディアへと進化する背景には、間違いなくSNSの台頭とデジタル技術の進化がある。
従来のメディアが一方的に情報を発信する「装置」として機能していたのに対し、現代のメディアは「共感を生むためのプラットフォーム」へと変貌したのは冒頭でも解説した通り。
これにより、ブランドも単なる商品やサービスの象徴ではなく、価値観やストーリーを共有し、顧客と共にコミュニティを形成する存在となったわけだ。
下手をすれば炎上し、上手くやればファンは増え、売上は上がる。
どんな情報を発信するか、ある意味でその企業の「センス」が問われているとも言える。
その背景としては、特に消費者がブランドに求める価値が変化している点が大きい。
かつては品質や価格がブランド選択の要因だったが、現代では「共感」や「価値観の一致」が重要視されるようになった。
ブランドが一方的に発信するだけでなく、消費者と対話し、価値観を共有できる存在であることが求められているのだ。
これが、ブランドがメディア化する大きな理由ではないだろうか?
ブランドがメディアになるための戦略
ブランドをメディアとして活用することで、企業は信頼性の向上や価値観の共有を強化できる。
特にストーリー性のある情報発信は、ブランドイメージを確立しやすい。
一方で、発信力が強まることで誤情報や炎上リスクも増大するため、適切な管理が求められるのも事実だ。
ブランドをメディアとして位置づける際には、単なる情報提供ではなく、ブランドを通じて何を伝えたいのかを明確にする必要がある。
商品や機能の情報だけを投げつけているなら、それはもうブランドとしての戦略ではない。
共感を生むストーリーを軸に据え、顧客が参加しやすいメディア運営を目指すことが重要なのは言うまでもないだろう。
UGC(User Generate Contents)という言葉が少しずつ一般化し始めているのも、その象徴といえる。
例えば、AppleやNikeは、商品そのものだけでなく、ブランドが持つ哲学やビジョンを発信することで、ブランドそのものがメディアとして機能している好例だと思う。
AppleやNIKEのSNS発信は、情報を届けるだけでなく、ブランドの価値を体現しているのだ。
これはかつてのテレビCMの変化にも似ている。
機能と企業名を連呼、ゴリ押しするCMが淘汰され、商品の背景や、企業イメージを先行して届けるようになったのには、消費者=視聴者がその広告に飽きてしまったからだ。
企業ブランドにもこれと同じことが起きている。
そのブランドの商品や機能を連呼するだけでは、誰も見向きもしない。
キチンと自分たちの発信するべき本質的価値(コアバリューという)を言語化し、丁寧にビジュアル化して届けないと、消費者は見向きもしてくれないわけだ。
まとめと展望
ブランドが新時代のメディアとして機能することは、企業価値を高めるだけでなく、顧客との繋がりをより強固にする可能性を秘めている。
そのためにも、ブランドが発信する情報が、単なる宣伝ではなく価値あるメッセージとして受け取られる未来を目指すべきだ。
だからブランド戦略、つまりはメディアとしての機能をどう設計するかがこれからの時代には大事になる。
筆者はテレビ番組のディレクターからキャリアをスタートし、ウェブ、SNSといったあらゆるジャンルのメディアの立ち上げやディレクションに従事してきた。
もし良かったら、このあたりの話を詳しくすることも出来る。
良かったら、気軽に問い合わせてほしい。
それではまた。