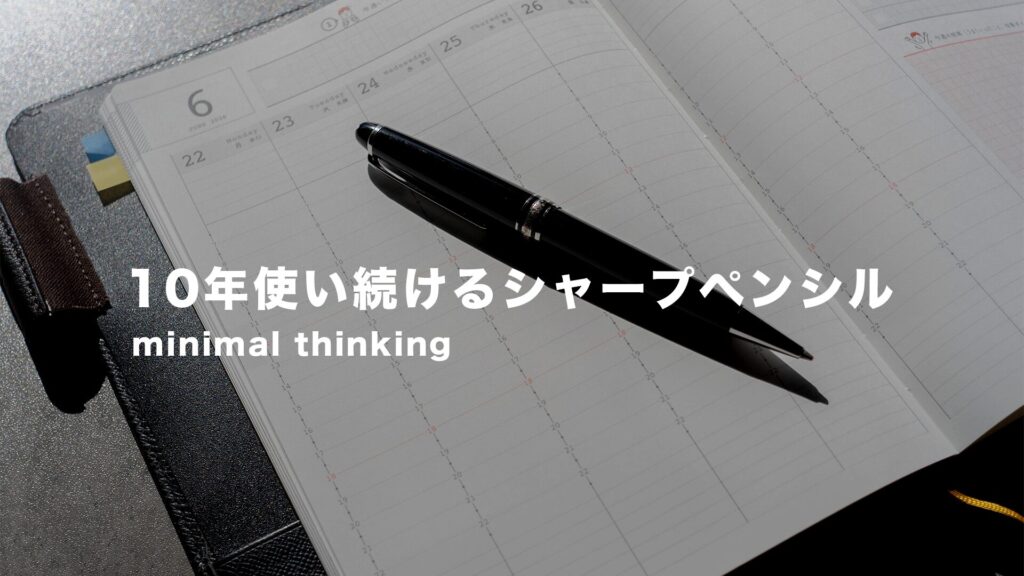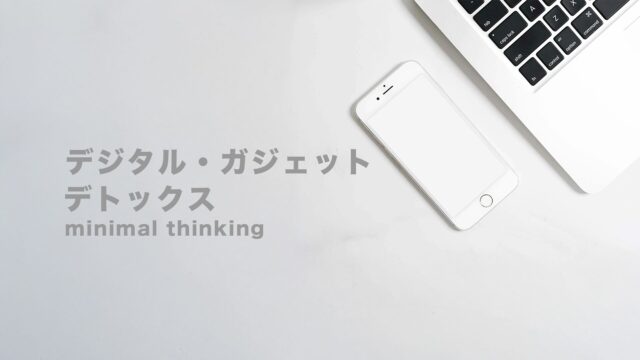40代ミニマリストのワードローブ選び ─ 服は“使い潰す”から美しい

ミニマリズムは「減らすこと」ではない。
“意味のあるものだけ残す”ために、静かに選び直す行為だ。
だから僕は、服を“買う”ことをやめた。
代わりに、使い潰してから更新する。
欲しいから買う時代は終わり、役割を終えたから交換する、という循環に変わった。
実は、服にも、寿命がある。
今の僕は、靴を含めて25アイテム。
数は多くないけれど、そのぶん濃度がある。
肩にできた丸みも、
袖口の擦れも、
少し褪せた色も、
それは「劣化」ではなく、その服と一緒に生きた時間の跡だ。
例えば、Quartzのコートは10年後の冬まで着倒す。
あるいは、Levi’sの501が、少しずつ自分の形に育っていく。
そういう“時間の質感”が、40代のワードローブを美しくする。
1|40代は、装いに“自分だけの都合”を許されない
40歳を過ぎると、似合う服が少なくなるのは仕方ない。
それだけではなく、服は自分の表現だけで完結しなくなる。
ミニマリストだからといって、誰もがスティーブ・ジョブズにはなれない。
そうなると、ジーパンとタートルネックで仕事に行くわけにもいかない。
僕らの装いは、相手への敬意であり、関係性を守るためのメディアでもあるから。
だから僕は、役割ごとに4つに分けて服を管理している。
1)ビジネス──端正さで整える領域
COMME CA のセットアップが中心。
そのまま打ち合わせに行ける“即戦力”。
2)インフォーマル──きちんとした私服の場
美術館、少し良いレストラン、回らないお寿司屋さんでの静かなデート。
Yohji Yamamoto の黒が、余白のある落ち着きをくれる。
3)カジュアル──風を感じる日の選択
Levi’s の履き心地に任せ、
BALENCIAGAで“遊び”の空気をまとう。
4)スポーツ──汗をかくための服
ジムやランニング、バスケ、たまに海に行く非日常。
Hurleyを纏うことで、動きやすさと快適さを優先している。
結果として、服の数は減っていくのに、意味の濃度は上がっていく。
参考記事:40代ミニマリストの靴選び|スニーカー派が“一足だけ”選んだ革靴の理由
2|装いは「余白」で信頼を生む
40代の装いには、派手なロゴも過剰な主張もいらない。
大事なのは、空気を乱さない“佇まい”だ。
会う相手に対して失礼がないこと。
場の温度を壊さないこと。
ロゴではなく、余白で信頼を生むこと。
服は、自分のためだけにあるのではなく、
“関係性を守るための道具”でもある。
この視点を持つだけで、ワードローブの選択は驚くほど静まり返る。
3|使い潰してから更新する。循環するワードローブへ
僕が目指しているのは、
「更新するワードローブ」──循環する人生だ。
それぞれの服や靴は、それぞれの寿命をもつ。
修理して10年単位で着る服もある。
1、2シーズンで気潰す服もある。
例えば、あと4年もすればQuartzのコートを使い切り、
次のブルゾンへとバトンを渡すだろう。
次の夏には白スニーカーを履き潰すと思う。
一方で、インフォーマルで使用するローファーは修理しながら10年は履くだろう。
どの服や靴にも“最後の瞬間”がある。
その終わりをしっかり見届けてから買い替える。
それはもう、単なるファッションではない。
時計が時間を刻むように、
服もまた、僕と一緒に人生を刻んでいくのだ。
服を手放す日の前には、必ず“ありがとう”と言う。
そこには、単なる消費を越えた敬意がある。
売るために買わない。
捨てるために買わない。
更新のタイミングは、
自分の人生の周期と同期させる。
それはまるで時計をオーバーホールするように、
服もまた、人生のフェーズごとに点検していく。

40代になると、「何を持つか」は「どう生きるか」とほぼ同じ意味を持つ
少なく持つことが目的ではない。
迷わずに生きるために、“意味のあるものだけ残す”。
ワードローブが軽くなるほど、
暮らしは深みを増していく。
40代のミニマリズムは、削ることではなく、
人生の密度を整える思想だ。
だから僕は、今日も同じ25アイテムで心地よく生きている。
服は“使い潰す”方が、美しい。
おすすめ記事を読む
40代ミニマリストの服は減らすではなく、選び直す|服の賞味期限という考え方
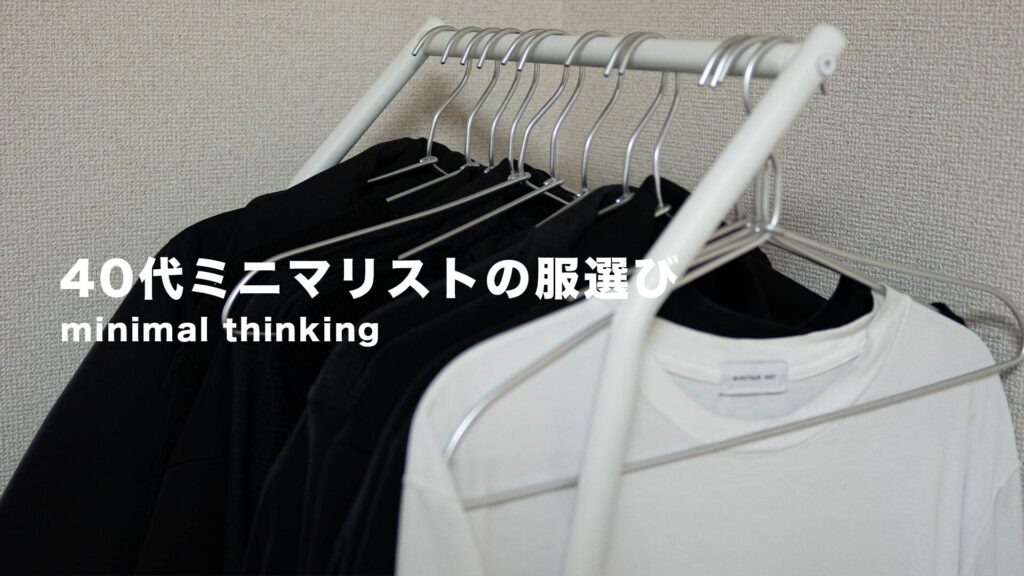
40代からのミニマルライフ|暮らしを整える“思考のシンプル化”

10年支えてくれたシャーペンの話──思考を深める“仕事道具”の選び方